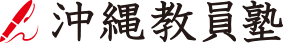2025年度実施 沖縄県公立学校教員候補者選考試験 合格体験記 高等学校・国語
(1)はじめに
私は高校国語の試験を10回受けて合格することができました。恥ずかしい話ですが、これまでは大した準備もせずに試験を受け続けていました。沖縄教員塾が那覇にあった時にも1年ほど通っていましたが、名護から那覇に通うことで満足してしまっていたような気がします。また、授業準備や進路指導、部活動、家事や育児を言い訳に採用試験の勉強からどんどん遠ざかっていきました。ここ最近の高校国語の受験者数と採用数から合格への可能性は高まっていると思ってはいましたが、今の私ではどんなに高まっても無理だとも気づいていました。そんな私を変えてくれたのは同僚の先生方から「本当にこのままでいいのか」という言葉をもらったことと、息子の小学校入学を機に自分自身を見つめ直すきっかけがあったことです。覚悟を決めた後はすぐに入塾しました。
沖縄教員塾には一度お世話になっていたので、合格するならここに入塾するのが近道だと思っていました。入塾してからは、採用試験の勉強はもちろんのこと、自分の弱さに気づかせてくれ、人としても成長できるチャンスをいただきました。また、授業後の面談では、学習の進捗状況や仕事の話まで親身に聞いてくださり、その状況にあった勉強のスタイルを提案していただきました。授業前の本の紹介や県教育委員会の傍聴、新聞記事についてのお話は毎回楽しみで、自分がいかに無知なのかを思い知ることも多くありましたが、情報をアップデートできている喜びのほうが上回っていました。こちらの合格体験記にもたくさんお世話になりました。気持ちが落ち混んだ時には先輩方の記事を読ませてもらい、自分だけじゃないのだから甘えるなと、歯を食いしばることができました。上高先生をはじめ、二次対策でお世話になった沖縄教員塾の先輩方、これまで合格体験記を書いてくださった先輩方には感謝申し上げます。
以下に私の経験を記します。臨任、子育てをしながらの受験だったため、家族や職場の同僚、友人にも感謝してもしきれないぐらいです。私みたいな何の取柄もない人間が合格できたので、きっとみなさん合格できます。これから採用試験に挑む方、入塾を考えている方に少しでも参考になれば幸いです。
(2)一次試験
私は一部免除があったため専門教養のみの勉強でした。課題は勉強時間の確保で、仕事や家事、子育てなどの理由から勉強時間は決まっていました。最初の頃は焦るあまり睡眠時間を削っていましたが、だんだん集中力が持たなくなり、必要最低限の睡眠時間は確保することにしました。そうなると、土曜日の授業の復習と週2回の漢字や沖縄の文学の小テストなどの復習でいっぱいになり、毎週火曜日の過去問を解けずに終わることが増えていきました。とても焦りましたが、上高先生と相談し過去問は4月以降に回すことになり、安心して授業や小テストの復習に時間をかけられました。とにかく、この一年間は沖縄教員塾の教材だけにしぼり徹底して取り組みました。過去の先輩の「問題から吸い尽くせるものは全て吸い尽くす」という言葉が、私にとって勉強をする上での模範であり励みになりました。
教材は週に一度の郵送でした。土曜日はオンライン授業(9:00~12:00)がありました。授業後に上高先生と個別面談の日もあり、勉強の進捗状況はここで報告し相談をしていました。漢字、学習指導要領、沖縄の文学、授業内容の確認テストもあり、繰り返し問題を解くことで暗記しづらいものも自然と定着していきました。さらに、答案を採点していただけることで、細かなミスにも気づくことができました。復習が次の授業に間に合わないこともたびたびありましたが、その都度報告し、復習を優先して余裕のある時に追いつくといった感じでした。
〇学習指導要領
・通勤時間を利用
・月に一度は一通り読む
問題の中でも確実に点数が取れる所なので30点満点を狙っていましたが、初めのうちは小テストですら満点が取れませんでした。それどころか、古文や漢文の学習に力が入ってしまい学習指導要領の勉強は疎かになっていました。時間を作れないか考えた結果、多くの先輩方が実践していた通勤時間を利用することにしました(通勤往復1時間)。小テスト分を音読して録音し、次の日の通勤時に車で聞いて口に出して繰り返すようにしました。それでも厳しいように感じたので、1か月に一度は塾のテキストをシートで隠して一通り読み、長期記憶に繋がるように意識しました。採用試験前は、特に教科の目標と現代の国語を確認していました。(昨年で現代の国語から古典探究まで一周し終えたため)。上高先生のお話では、他教科は中学校学習指導要領からの出題もあったと聞いていたので、中学校国語の学習指導要領にも目を通していました。
※今年の出題は8問×3点(昨年から2問減った)
〇現代文
・時間内に解く
現代文は時間をかけられなかったというのが正直なところです。試験までに解いた問題は、塾でいただいた模試と過去問のみだったと思います。とにかく時間内に解くことだけを意識しました。問題を解くときに何度も本文に戻らないようにするために、接続詞の印のつけ方を工夫したり、重要部分の線引きや大段落のチェックをしたりしました。解答後の復習は、間違えた問題がどこで読み間違ったのかを確認することと、本文の分からなかった語句をノートに書いて辞書で調べることの2つです。
〇古文・漢文
・出典(ジャンル、年代、内容)→国語便覧
・品詞分解→(文法、主語と指示語の確認)
・塾のテキスト(重要語句を抑えているか確認、解説を全て読む)
・音読(本文、文法まとめプリント)
古文と漢文には時間をかけました。最初の頃は、授業の復習をするのに1週間かかる時もありました。古文の復習は、品詞分解をして塾の解説を確認する流れです。その際に、文法だけでなく主語や指示語の確認も行いました。分からないところはメールでまとめて上高先生に質問していました。漢文も塾のテキストのみの学習で、句法の確認から始めました。塾オリジナルの漢文句法のまとめプリントをどこでも持ち歩くようにして、暇さえあれば音読していました。例文で覚えるのでとても分かりやすかったです。古文も漢文も、毎週行う確認テストの復習は丁寧に行い、必ず声に出して本文を読むように意識していました。
〇沖縄の文学
・『沖縄の文学』高教組教育資料センター
・覚えるべき内容は付箋にメモする。
沖縄の文学は、小テストの復習を中心に進めました。できなかったところは、付箋にメモをしてテーブルに貼り、翌朝すぐに覚えているか確認できるようにしていました(朝の勉強時間がないとき)。付箋はノートに貼り直して後日また復習に使います。仕事のお昼時間に余裕がある時には『沖縄の文学』を読み、塾の小テストの内容などを改めて確認していました。
(3)二次試験について
〇一次試験後から発表まで(受験調書)
私は一次試験のすぐ後は、一部免除で教職教養の勉強をしていなかったため、教育委員会のHPから学力関連や教育施策のページを読むようにしていました。上高先生による二次対策オリエンテーションと沖縄教員塾の先輩方による講話は、二次試験に初めて挑戦する私にとってはやるべきことがイメージしやすく、押さえるべきポイントも教えていただいたので大変貴重なお話でした。それからは受験調書の完成を目指しました。そのために、二次対策のオリエンテーションで教わった「選考で重視する視点」「沖縄県教育委員会の求める教員像」について考えました。この2つについて自分の言葉で説明できるか、私に当てはまる部分は何かをノートに書いていきました。言葉一つひとつが気になり、完成と言えるまで時間がかかりました。
〇面接
面接は苦手意識がありましたが、受験調書に時間がかかった分、メールでの一問一答は思っていたより答えられたと思います。しかし、いざ声に出してみると話し過ぎてしまい、回答が長くなってしまう傾向がありました。そこで、言い切ることを意識し、上高先生との一問一答を何度も繰り返すうちにコツがつかめるようになりました。模擬面接では本番よりも緊張感があり、考えるときに上を向く癖や声が小さくなってしまうなど、実践でないと気づけない部分を指摘してもらい、二次試験までに改善することができました。(しかし、試験当日は今までになかった心境になりました。自分をアピールしなくてはと気持ちが高ぶってしまい冷静でなかったことが反省点です。)
〇模擬授業
合格者講話のなかで、学習指導案の細案やシナリオを作ったとのお話があったので、課題が届き次第すぐに作成に取り掛かりました。生徒に「どんな力を身につけさせたいのか」軸を決めること、自分の勤務校をイメージすると考えやすかったです。沖縄教員塾だけでなく、友人や同僚の先生方にもたくさん見ていただき、何度も変更し修正しました。特に評価基準に関してはたくさん指摘をいただき、ギリギリまで試行錯誤して形になりました。面接同様、緊張すると声が小さくなってしまい、初めのうちは恥ずかしさもありましたが、回数を重ねるうちに声も出るようになりました。
(4)最後に
私がこれまで不合格だった原因は勉強不足と覚悟が足りなかったことです。この1年は勉強量を倍に増やし、自分自身に言い訳しないことを決めて取り組みました。絶対にこの1年間で合格を決め、本務として生徒に長く寄り添いたいと思っていました。
授業や面談でいただく上高先生の厳しい言葉には愛情があり、そのおかげで私は入塾して教員としても人としても成長できました。ただ、合格した今でも力不足だと強く感じています。この気持ちを常に持ち続け、沖縄県の生徒の成長を支えられるように私自身も成長していきます。
最後に、上高先生を始め、お世話になった沖縄教員塾の先輩方、家族や友人、同僚の先生方に深く感謝申し上げます。これから入塾を考えている方、採用試験を目指す方、拙い文章ではありますが、何か参考になることがありましたら幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。
- 投稿タグ
- 2025年度実施選考試験